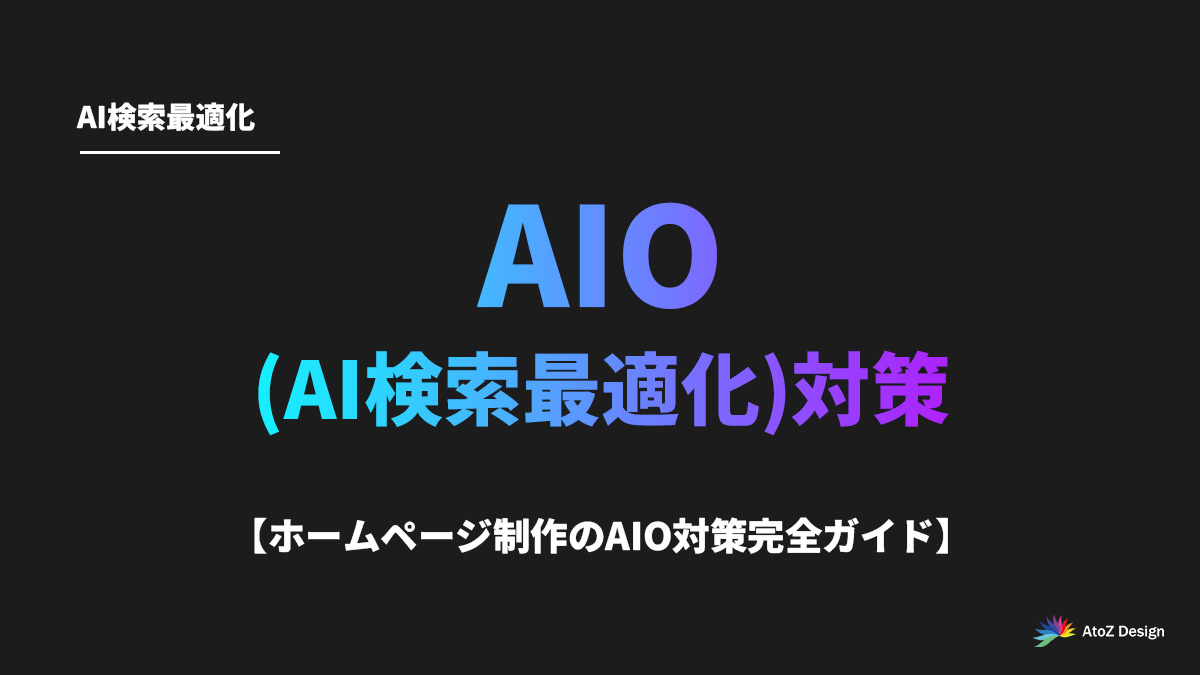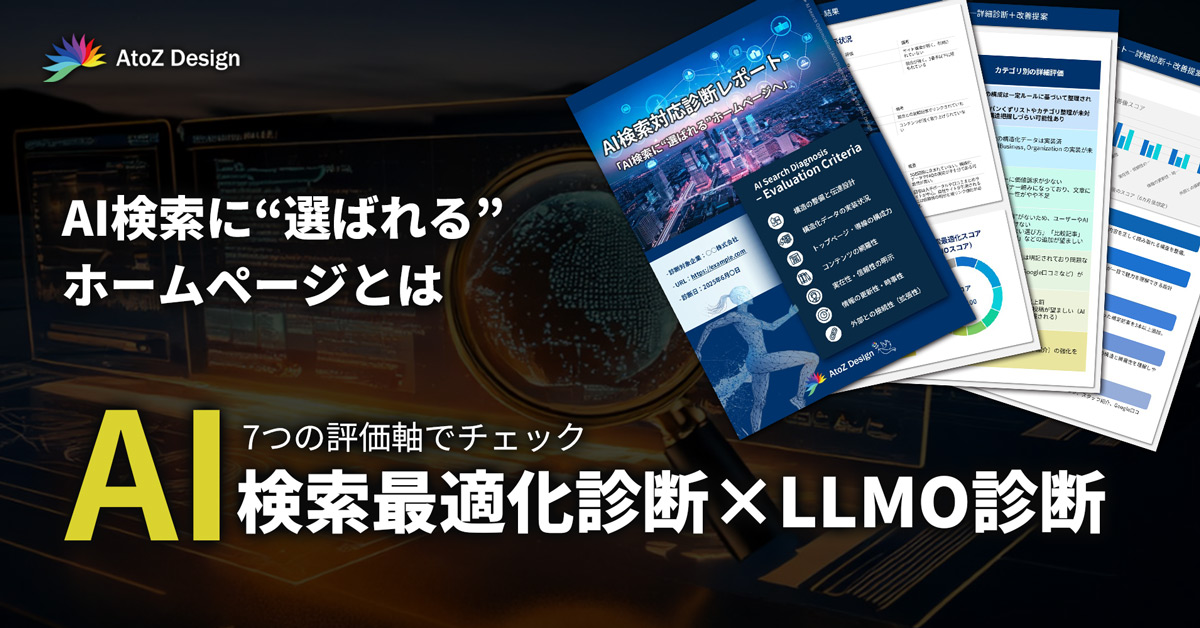「ホームページ作ったけど、全然集客できない…」
「ホームページを維持するために制作会社に毎月コストを払っているけど…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
近年、GoogleのSGE(Search Generative Experience)やChatGPTに代表されるAI検索の進化により、これまでのSEO対策だけではお客様に“見つけてもらえない”時代が到来しています。
地域密着型のビジネスにとって、「地元のお客様に選ばれる仕組み」をどうホームページで伝えるかが、これからの集客においてとても大切なカギになります。
この記事では、2025年最新のトレンドをふまえながら、
-
AIに“理解される”ホームページ設計の基本
-
地域の検索ニーズに対応するコンテンツの作り方
-
やりがちなNG設計とその改善ポイント
-
実際に成果が出た成功事例
-
今日から使える実践アドバイス
など、地域ビジネスのためのホームページ戦略をわかりやすくまとめています。
あなたのビジネスを「検索で選ばれる存在」へ変えるために、今こそホームページを見直してみませんか?
なぜ今、「地域ビジネス × AIO(AI検索最適化)」対策が重要なのか?

従来のSEO対策は、Googleなどの検索エンジンを対象としたものでしたが、AI検索の登場により、ホームページ集客の戦略を大きく見直す必要が出てきました。AI検索は、従来の検索エンジンとは異なる仕組みで情報を収集・分析し、ユーザーに最適な情報を提供するため、従来のSEO対策だけでは、地域ビジネスのホームページが埋もれてしまう可能性があるのです。
AI検索(SGE/ChatGPT)の進化と従来の検索エンジンの違い
AI検索、特にGoogleのSGE(Search Generative Experience)やChatGPTなどの対話型AIは、従来の検索エンジンとは一線を画す進化を遂げています。従来の検索エンジンは、キーワードに基づいて関連性の高いWebサイトをリスト表示するのに対し、AI検索は、ユーザーの質問の意図を理解し、関連情報をまとめて提示したり、対話形式で質問に答えたりすることができます。
この違いを理解することが、AI検索時代に地域ビジネスが生き残るための第一歩です。従来のSEO対策では、キーワードの出現頻度や被リンク数などが重視されていましたが、AI検索では、コンテンツの質、情報の網羅性、ユーザーの検索意図との合致度などがより重視されるようになります。
| 比較項目 | 従来の検索エンジン | AI検索(SGE/ChatGPT) |
|---|---|---|
| 情報提供方法 | Webサイトのリスト表示 | 関連情報のまとめ、対話形式での回答 |
| 重視される要素 | キーワード、被リンク数 | コンテンツの質、網羅性、検索意図との合致度 |
| ユーザー体験 | 自分で情報を探す | AIが情報を整理・提供 |
「地域名+業種」だけでは不十分?AI時代の検索ニーズを解説
これまで、地域ビジネスのSEO対策といえば、「地域名+業種」のキーワードで上位表示を目指すのが一般的でした。しかし、AI検索の進化により、この対策だけでは十分とは言えなくなってきています。なぜなら、AI検索は、ユーザーの検索意図をより深く理解し、より具体的なニーズに応える情報を提示しようとするからです。
例えば、「渋谷 カフェ」と検索するユーザーは、単に渋谷にあるカフェを探しているだけでなく、「渋谷で友人とゆっくり話せるカフェ」や「渋谷で電源が使えるカフェ」など、具体的な目的を持っている可能性があります。AI検索は、このようなユーザーの潜在的なニーズを汲み取り、最適なカフェを提案しようとします。
つまり、AI検索時代においては、「地域名+業種」だけでなく、ユーザーの具体的な目的やニーズを考慮したキーワード戦略が不可欠となるのです。
ターゲットは「目的+地域+ニーズ」検索!変化への対応が不可欠
AI検索時代に地域ビジネスがターゲットとすべきは、「目的+地域+ニーズ」を組み合わせた検索です。例えば、「子供のカット+〇〇(地域名)+安い」、「〇〇(地域名)+肩こり+マッサージ+当日予約」といった具体的なキーワードで検索するユーザーをターゲットに、ホームページのコンテンツを最適化する必要があります。
そのためには、まず、自社のビジネスがどのような目的やニーズに応えられるのかを明確に定義し、それらの目的やニーズをキーワードとしてホームページに組み込む必要があります。また、FAQページを充実させたり、お客様の声を紹介したりすることで、ユーザーの疑問や不安を解消し、信頼感を高めることも重要です。
AI検索の進化は、地域ビジネスにとって大きなチャンスでもあります。変化に対応し、ユーザーのニーズに応えるホームページを構築することで、AI検索を通じて多くのお客様にビジネスを知ってもらい、集客につなげることが可能になります。
AIO(AI検索最適化)で評価されるホームページ設計 5つの鉄則

鉄則1:トップページ最適化 – 冒頭で「誰に」「何を」「どこで」提供するか明確に
AI検索は、Webサイトの冒頭部分を特に重視します。なぜなら、AIは瞬時にサイトの目的と価値を理解する必要があるからです。トップページの上部に、以下の3つの要素を明確に記載しましょう。
- 誰に: ターゲット顧客を明確にする(例:岡山市で肩こりに悩む30代女性)
- 何を: 提供する価値・サービスを具体的に示す(例:オーダーメイド施術による肩こり解消)
- どこで: 地域名を明記する(例:岡山市北区の整体院)
これらの要素を盛り込むことで、AIはあなたのビジネスが「誰の」「どんな」悩みを「どこで」解決できるのかを正確に認識し、適切な検索結果に表示する可能性が高まります。
鉄則2:共感と行動を促す導線設計 – ユーザー目線のわかりやすさが鍵
AI検索は、ユーザーエクスペリエンス(UX)を重視します。つまり、ホームページが訪問者にとって使いやすく、目的を達成しやすい設計になっているかが重要です。以下の点に注意して、共感と行動を促す導線設計を心がけましょう。
- ユーザー目線のコンテンツ: 専門用語を避け、ターゲット顧客が理解しやすい言葉で情報を伝えましょう。
- 明確なCTA(Call to Action): 予約、問い合わせ、資料請求など、ユーザーに期待する行動を促すボタンやリンクを分かりやすく配置しましょう。
- レスポンシブデザイン: スマートフォン、タブレット、PCなど、あらゆるデバイスで快適に閲覧できるデザインを採用しましょう。
AIは、これらの要素を総合的に評価し、ユーザーにとって価値のあるホームページを上位表示します。
鉄則3:サービスページとFAQ設計 – 課題解決コンテンツで信頼性UP
AI検索は、ユーザーの検索意図を深く理解し、最適な情報を提供しようとします。そのため、サービスページとFAQ(よくある質問)を充実させ、ターゲット顧客の課題解決に役立つコンテンツを作成することが重要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。
- サービスページ: 各サービスの詳細な説明、料金、施術の流れなどを具体的に記載しましょう。
- FAQ: 顧客が抱える疑問や不安を解消するFAQを充実させましょう。質問と回答をセットで記述することで、AIが情報を理解しやすくなります。
- キーワードの活用: ターゲット顧客が検索するであろうキーワードを自然な形で盛り込みましょう。
これらの課題解決コンテンツは、AIからの評価を高め、検索順位の向上に繋がります。
鉄則4:実績・事例紹介ページ – Before/Afterで変化を可視化、地域名も明記
AI検索は、Webサイトの信頼性、専門性、権威性(E-E-A-T)を評価します。実績・事例紹介ページは、これらの要素を高める上で非常に有効です。以下のポイントを意識して、説得力のある実績・事例紹介ページを作成しましょう。
- Before/After: サービス利用前後の変化を写真や数値で可視化しましょう。
- 顧客の声: 実際にサービスを利用した顧客の感想や評価を掲載しましょう。
- 地域名の明記: 実績・事例がどの地域のものかを明記することで、地域顧客への訴求力を高めましょう。
これらの要素を盛り込むことで、AIはあなたのビジネスが地域顧客の課題を解決できる信頼できる存在であると認識し、検索結果に表示する可能性が高まります。
鉄則5:内部リンクとカテゴリ構造 – AIも理解できる整理された構造
AI検索は、Webサイト全体の構造を理解し、関連性の高い情報を結びつけようとします。そのため、内部リンクとカテゴリ構造を整理し、AIが情報を理解しやすいようにすることが重要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。
- カテゴリ構造: サービス、事例、ブログなど、Webサイトのコンテンツを分かりやすいカテゴリに分類しましょう。
- 内部リンク: 関連性の高いページ同士をリンクで結びつけ、ユーザーがスムーズに情報を辿れるようにしましょう。
- パンくずリスト: ユーザーが現在どのページにいるのかを分かりやすく示すパンくずリストを設置しましょう。
これらの要素を整備することで、AIはあなたのWebサイトの全体像を把握しやすくなり、より正確な検索結果を表示する可能性が高まります。
AIは、Webサイトの信頼性、専門性、権威性(E-E-A-T)を評価し、ユーザーにとって最も価値のある情報を提供しようとします。企業は、GoogleとBingのAI検索の違いを理解し、それぞれの検索エンジンに最適化されたコンテンツ戦略を立てる必要があります。具体的には、Googleに対しては、質の高いコンテンツを作成し、E-E-A-Tを高めることが重要です。Bingに対しては、自然な会話形式での情報提供を意識し、ユーザーとのエンゲージメントを高めることが重要です。
AI検索で埋もれるホームページのNG例

せっかくホームページを作ったのに、AI検索で全く表示されない…。そんな悲しい事態を避けるために、ここでは、AI検索で埋もれてしまうホームページのNG例を具体的に解説します。
NG例1:「ごあいさつ」と「会社概要」だけでは価値が伝わらない
ホームページを開くと、立派な「ごあいさつ」と「会社概要」が目に飛び込んでくる。かつては、それだけで“会社の顔”として十分だったかもしれません。しかし、AI検索時代においては、これだけでは情報量が圧倒的に不足し、ユーザーの検索意図に応えられず、AIにも評価されません。
AIは、ホームページの内容を深く理解し、ユーザーの検索クエリとの関連性を判断します。単なる「ごあいさつ」や「会社概要」だけでは、AIは「この会社が何を提供してくれるのか」「自分の悩みを解決してくれるのか」を判断できません。結果、AI検索で上位表示されることは難しくなります。
ホームページの冒頭では、訪問者に対して「誰に」「何を」「どこで」提供するのかを明確に伝える必要があります。例えば、以下のように具体的に記述しましょう。
- 誰に:「〇〇にお住まいの、△△でお困りのあなたへ」
- 何を:「〇〇(商品・サービス名)で、△△(悩み)を解決します」
- どこで:「〇〇(地域名)で、△△(商品・サービス)を提供しています」
これにより、AIはホームページの内容を正確に理解し、関連性の高い検索クエリに対して上位表示してくれる可能性が高まります。
NG例2:「こちらをクリック」多用はNG!ユーザーを迷わせる内部リンク
ホームページ全体に「こちらをクリック」「詳しくはこちら」といった曖昧な表現の内部リンクが散見されるのも、AI検索で評価を下げる要因となります。これらの表現は、リンク先のページ内容を全く示唆しておらず、ユーザーだけでなくAIも混乱させてしまうからです。
AIは、内部リンクのアンカーテキスト(リンクに埋め込まれたテキスト)を重要な手がかりとして、リンク先のページ内容を理解します。「こちらをクリック」のような汎用的な表現では、AIはリンク先のページが何について書かれているのかを判断できません。結果、ホームページ全体のSEO評価が低下し、AI検索での表示順位も下がる可能性があります。
内部リンクを設置する際は、リンク先のページ内容を具体的に示すアンカーテキストを使用しましょう。例えば、以下のように記述します。
- NG:「当社のサービスについてはこちらをクリック」
- OK:「〇〇(サービス名)の詳細はこちらをご覧ください」
- NG:「事例紹介はこちら」
- OK:「〇〇(地域名)での施工事例はこちら」
このように、具体的なキーワードを含むアンカーテキストを使用することで、AIはリンク先のページ内容を正確に理解し、ホームページ全体のSEO評価を高めることができます。
NG例3:独自性のない“名刺代わり”のホームページは淘汰される
「とりあえずホームページを作った」という、情報が少なく、他社との差別化が図られていない“名刺代わり”のホームページは、AI検索時代において淘汰される運命にあります。AIは、ホームページの独自性や専門性を重視するため、類似コンテンツばかりのホームページは評価しないからです。
AIは、インターネット上に存在する膨大な情報を学習し、ホームページの内容を比較・分析します。その結果、独自性のないホームページは、他のホームページとの差別化が図られていないと判断され、評価が低くなります。特に、地域ビジネスにおいては、地域に根差した独自の強みや魅力をアピールすることが重要です。
ホームページに独自性を出すためには、以下の点を意識しましょう。
- 強みを明確にする:競合他社にはない、自社の独自の強みや特徴を明確にしましょう。
- ターゲットを絞る:誰に向けて情報発信するのかを明確にし、ターゲットに合わせたコンテンツを作成しましょう。
- 地域性を出す:地域名や地域特有の情報を積極的に盛り込み、地域密着型であることをアピールしましょう。
- 事例を掲載する:過去の成功事例やお客様の声などを掲載し、実績をアピールしましょう。
これらの要素を盛り込むことで、AIはホームページの独自性や専門性を高く評価し、AI検索での上位表示に繋がりやすくなります。
成功事例に学ぶ!AIに評価された地域ビジネスサイト

AI検索で上位表示され、集客に成功している地域ビジネスサイトには、共通する特徴があります。ここでは、業種別に3つの成功事例を紹介し、AIがどのように評価しているのか、具体的なポイントを解説します。
事例1:工務店 – 施工事例×地域密着ストーリーでChatGPTも高評価
サイト概要:
地域密着型の工務店A社は、デザイン性の高い住宅の施工事例を多数掲載しています。各事例には、施主のライフスタイルや家づくりに対する想いを反映したストーリー性のある紹介文が添えられており、訪問者の共感を呼ぶ構成となっています。また、地域イベントへの参加や、地元の木材を活用した家づくりなど、地域への貢献活動についても積極的に発信しています。
AI評価ポイント:
-
視覚的な訴求力: 高品質な写真で施工事例を丁寧に紹介し、ユーザーの関心を惹きつけています。
-
ストーリーによる共感: 施主の想いや家づくりの背景を丁寧に伝えることで、感情的なつながりを生み出しています。
-
地域密着性のアピール: 地域イベントへの参加や地元資源の活用など、地域とのつながりを具体的に示すことで、信頼感を高めています。
ChatGPT分析:
ChatGPTにA社のホームページURLを入力し、「この工務店の特徴は?」と質問したところ、以下のような回答が得られました:
「デザイン性の高い住宅施工事例が豊富で、お客様のライフスタイルに合わせた家づくりを提案している点が特徴です。地域密着型で、地元の木材を使用するなど、地域貢献にも力を入れています。」
AIがA社のホームページ内容を正確に把握し、強みを理解していることがわかります。
成功のポイント:
-
高品質な施工事例の掲載: デザイン性と機能性を両立した住宅事例を、豊富な写真とともに紹介。
-
顧客ストーリーの重視: 施主の想いや家づくりの背景を丁寧に取材し、共感を呼ぶコンテンツを制作。
-
地域キーワードの活用: 「〇〇市 工務店」「〇〇地域 注文住宅」など、地域名を含むキーワードを活用し、SEO効果を高めています。
事例2:士業 – FAQと充実のサービスページで「悩みベース検索」を攻略
サイト概要:
B事務所は、相続問題に特化した弁護士事務所です。ホームページでは、相続に関するよくある疑問や悩みに答えるFAQコンテンツを充実させており、ユーザーが自分の状況に近い情報をすぐに見つけられる構成になっています。
また、各サービスページでは料金体系や手続きの流れを明確に記載し、初めて法律相談を検討する方でも安心できる雰囲気がつくられています。
AI評価ポイント:
-
FAQコンテンツの網羅性: 相続の基本知識から、具体的なトラブル対応まで幅広い内容を掲載。ユーザーの検索意図に的確に応える内容設計になっています。
-
明確なサービス説明: 料金や対応範囲、相談の流れなどが具体的に示されており、信頼感につながっています。
-
専門性の伝達: 難解な専門用語も、一般の人にわかるよう平易な言葉で解説されており、ユーザーの理解をサポートします。
ChatGPT分析:
B事務所のホームページURLをChatGPTに入力し、「この事務所の強みは?」と質問したところ、次のような回答が得られました:
「相続問題に特化しており、FAQコンテンツが充実している点が強みです。料金体系や手続きの流れも明確に記載されており、安心して相談できる印象を与えます。」
この結果から、AIがB事務所の専門性とユーザー配慮の姿勢を正しく理解していることが分かります。
成功のポイント:
-
検索意図を捉えたキーワード設計: 「相続 手続き」「遺産分割 弁護士」など、ユーザーが実際に検索しそうな悩みベースのキーワードをFAQに自然に組み込んでいます。
-
専門用語の解説: 「遺留分」「遺産分割協議書」など、一般的に難しい用語も、わかりやすい言葉で丁寧に説明。初心者にも配慮された設計です。
-
料金表示の透明性: 「初回相談無料」や「着手金・報酬体系」のように、費用に関する情報を明確に提示。安心して問い合わせしやすい印象を与えています。
事例3:学習塾 – 保護者目線のブログ・Q&Aでローカル検索流入増
サイト概要:
C学習塾は、地域に根差した小中学生向けの学習塾です。ホームページでは、保護者向けのブログ記事やQ&Aコンテンツが充実しており、学習法のアドバイスや学校行事の情報、地域の子育てに関する内容など、保護者の関心を引くテーマを数多く取り上げています。
AI評価ポイント:
-
保護者目線のコンテンツ: 保護者が知りたい情報を的確に押さえ、共感を生む構成になっています。
-
地域密着型の情報発信: 地元の学校行事や地域イベント、子育て支援情報など、地域に特化した情報を発信することで、信頼性を高めています。
-
SEO対策の工夫: 「〇〇市 学習塾」「〇〇小学校 塾」など、地域名と関連キーワードを効果的に組み合わせ、検索対策を強化しています。
ChatGPT分析:
C学習塾のホームページURLをChatGPTに入力し、「この学習塾の特徴は?」と質問したところ、以下のような回答が得られました:
「保護者向けのブログ記事やQ&Aコンテンツが充実しており、地域に根差した情報を提供している点が特徴です。保護者が安心して子どもを預けられるような情報発信を心がけています。」
このことから、AIがC学習塾の地域密着性や保護者配慮の姿勢を正しく理解していることが分かります。
成功のポイント:
-
保護者ニーズの把握: 保護者が何に悩み、どんな情報を求めているかをリサーチし、それに応えるコンテンツを作成。
-
地域キーワードの活用: 地名や学校名といった地域ワードを効果的に活用し、SEOでの可視性を高めています。
-
SNS連携で発信力UP: ブログ記事やQ&AコンテンツをSNSでも展開し、集客とブランディングを両立しています。
地域ビジネスとAIO(AI検索最適化)に関してのよくある質問
地域ビジネスにAIO対策を導入するとどんな効果がありますか?
地域名+業種だけでなく「目的+地域+ニーズ」に対応した検索で見つかりやすくなります。ChatGPTやSGEに“理解される”設計にすることで、集客導線や予約・問い合わせへの到達率が向上します。
従来のSEOとAIOの違いは何ですか?
SEOはキーワードや被リンクが中心でしたが、AIOでは「文脈・網羅性・地域性」を重視します。FAQやサービスページ、実績紹介などを通じて、AIにとって理解しやすい構造と意味を持たせることが重要です。
NG設計の代表例はどのようなものですか?
「ごあいさつと会社概要だけ」のサイトや「こちらをクリック」といった曖昧な内部リンク、独自性のない名刺代わりサイトはAIに評価されません。誰に何を提供しているかを明確にし、具体的な導線を設計する必要があります。
成功している地域ビジネスサイトの共通点は何ですか?
高品質な事例紹介、FAQやブログなどの課題解決型コンテンツ、地域密着性を示す情報発信が共通点です。AIは独自性や専門性を理解し、正確に要約できるサイトを評価します。
既存のホームページでもAIO対応は可能ですか?
可能です。トップページの見直し、FAQの拡充、内部リンク整理、構造化データの追加など段階的な改善でAI対応できます。新規制作に比べてコストを抑えつつ成果につなげることが可能です。
AI検索時代に選ばれるホームページ設計 まとめ

「誰に」「どんな価値を」「どう伝えるか」再設計が成功への第一歩
本記事では、AI検索の進化に対応し、地域ビジネスがホームページで成果を上げるための戦略を解説してきました。重要なのは、従来のSEO対策に加えて、AIが理解しやすい構造と、ユーザーが求める情報を的確に提供することです。まずは、「誰に」「どんな価値を」「どう伝えるか」を明確に定義し、ホームページ全体の設計を見直しましょう。
ChatGPT/SGEは文脈を理解する!意味構造と導線設計が重要
ChatGPTやSGEといったAI検索エンジンは、単なるキーワードだけでなく、コンテンツの文脈や意味構造を理解します。そのため、ホームページ内の情報の関連性を高め、ユーザーが求める情報にスムーズにたどり着けるような導線設計が不可欠です。内部リンクを効果的に活用し、カテゴリ構造を整理することで、AIとユーザー双方にとってわかりやすいホームページを目指しましょう。
目指すは「AIにも、地域の人にも、伝わるホームページ」
AI検索対策は、単に検索順位を上げるためのテクニックではありません。最終的な目標は、地域の人々に価値を提供し、ビジネスを成長させることです。AIに評価されるだけでなく、地域の人々にも共感され、利用されるホームページこそが、真に成功するホームページと言えるでしょう。
【2025年版】AIO(AI検索最適化)対策に強いホームページ制作の完全ガイド では、AI検索最適化のやり方、業種別の対策や制作ノウハウまで詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
AIO(AI検索最適化)に強い地域ビジネスサイト設計は、AtoZ Designにお任せください

AtoZ Designでは、AI検索(SGE・ChatGPTなど)の最新動向を完全に把握した上で、地域ビジネスの特性に最適化したホームページ制作・リニューアルをサポートしています。
私たちは「見られるだけ」のサイトではなく、“選ばれるホームページ”をつくることに徹底的にこだわります。
-
地域の魅力や強みを、AIに正しく“伝わる形”で設計
-
集客・信頼・差別化を同時に叶えるコンテンツ戦略
-
医療・美容・建築・士業など、豊富な業種別実績あり
今あるホームページのAI検索対応チューニングのみのご相談も可能です。
「地域名+業種」で埋もれていると感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
“地域で選ばれる”ための設計、今すぐはじめましょう。