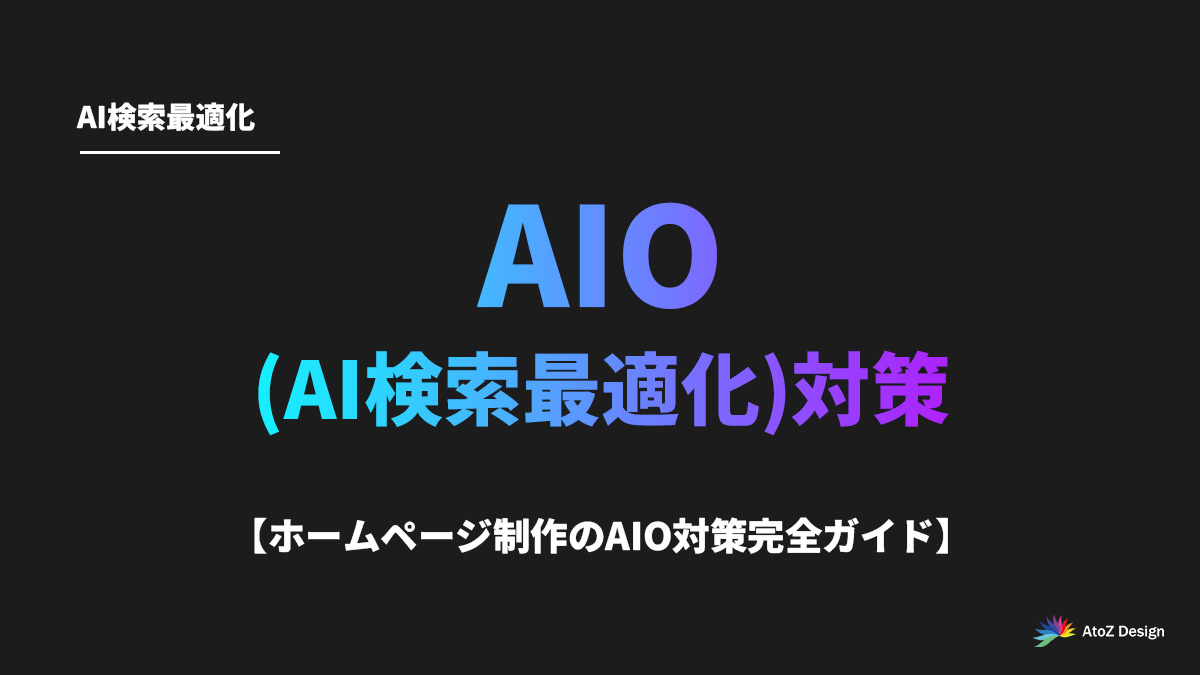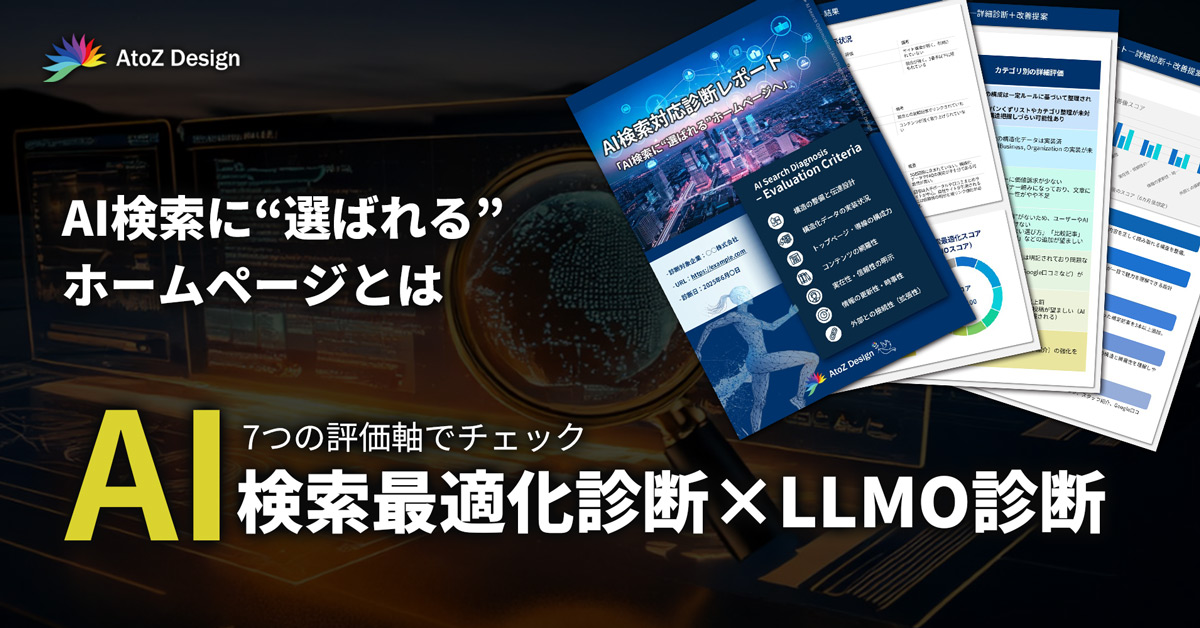「最近、患者さんが減ってきた気がする…」
「ホームページはあるけど、ほとんど更新していない…」
そんな不安や課題を感じている医療クリニックの院長先生へ。2025年、クリニックの集患は“AIO(AI検索最適化)”が勝敗を分ける時代に突入しています。
GoogleのSGE(Search Generative Experience)やChatGPTなど、AIによる検索が進化する中で、ホームページは単なる“情報掲載の場”から、“AIに評価される設計”が求められる存在へと変わりつつあります。
この記事では、医療広告ガイドラインを遵守しながら、AI検索で正しく評価され、患者さんの「今すぐ知りたい」に応えるクリニックホームページをどのように作っていけばよいのかを徹底解説。
-
ポータルサイトに頼りすぎていませんか?
-
AIに伝わるために必要な5つの設計ポイントとは?
-
陥りやすいNG例と、その改善策は?
-
実際に成果が出たクリニックサイトの事例は?
2025年、AI検索時代の“選ばれるホームページ”づくりを、一緒に見直してみましょう。
なぜ今、クリニックホームページはAIO(AI検索最適化)対応が必須なのか?~ポータルサイト依存からの脱却

近年、AI技術の進化は目覚ましく、特に検索エンジンの分野では大きな変革が起きています。従来のキーワード検索に加え、ChatGPTやSGE(Search Generative Experience)といったAI検索が台頭し、「症状ベースの質問」に対する回答能力が飛躍的に向上しました。この変化に対応するため、クリニックのホームページもAIを意識した設計が不可欠となっています。
AI検索(ChatGPT/SGE)が「症状ベースの質問」に対応開始
従来の検索エンジンでは、キーワードを正確に入力しないと、求める情報にたどり着けないことがありました。しかし、AI検索は、ユーザーが自然な言葉で症状や悩みを質問しても、その意図を理解し、適切な情報を提供できるようになりました。例えば、「急な発熱でだるい。近くの内科を探したい」といった質問に対し、AIはユーザーの所在地情報と症状を考慮し、適切なクリニックを提示できます。
この変化は、クリニックのホームページにとって大きなチャンスです。AIが理解しやすいように、診療科目、対象疾患、症状などをホームページに明記することで、AI検索からの流入を増やすことができます。
医療広告ガイドライン遵守とユーザー意図の両立の重要性
クリニックのホームページをAI対応にする上で、注意しなければならないのが医療広告ガイドラインです。医療広告は、患者の適切な医療選択を支援するために、厳格な規制が設けられています。誇大広告や虚偽の情報はもちろん、客観的な根拠のない効果の標榜も禁止されています。
AI対応を進める上で、SEO対策としてキーワードを多用したり、効果を過剰にアピールしたりすると、医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります。AIに理解されやすく、かつ医療広告ガイドラインを遵守したホームページを作成するには、専門的な知識とノウハウが不可欠です。
厚生労働省のホームページでも、医療広告ガイドラインに関する情報が公開されていますので、必ず確認するようにしましょう。
ポータルサイト(EPARK/病院なび等)依存のリスクと対策
多くのクリニックが、EPARKや病院なびなどの医療ポータルサイトに登録し、集患を行っています。ポータルサイトは、手軽に集患できるというメリットがある一方、依存度が高まると、以下のようなリスクがあります。
- 集客コストの増加:ポータルサイトへの掲載料や手数料が発生し、長期的に見るとコストが増加する可能性があります。
- ブランディングの困難さ:ポータルサイトのデザインや情報フォーマットに制約があり、自院の特色や強みを十分にアピールできない場合があります。
- SEO対策の遅れ:ポータルサイトに依存していると、自院のホームページのSEO対策がおろそかになり、AI検索からの流入機会を逃してしまう可能性があります。
ポータルサイト依存から脱却し、自院のホームページで集患を強化するためには、AI対応が不可欠です。AIに理解されやすいホームページを構築し、SEO対策を徹底することで、ポータルサイトに頼らずとも、安定的な集患を実現できます。
次のセクションでは、AIに理解されるクリニックサイトの5つの設計ポイントについて詳しく解説します。
AI検索に理解されるクリニックサイトの5つの設計ポイント

クリニックのホームページをAI検索に対応させるためには、いくつかの重要な設計ポイントがあります。これらのポイントを押さえることで、AIがクリニックの情報を正確に理解し、患者さんの検索意図に合致した情報を提供できるようになります。
ポイント1:トップページ構成 – 診療科目・対象疾患・予約動線の明確化
トップページは、クリニックの顔であり、患者さんが最初に訪れる場所です。そのため、診療科目、対象疾患、予約動線を明確にすることが重要です。
-
診療科目を分かりやすく表示する:
内科、外科、小児科など、提供している診療科目を一覧で表示します。それぞれの診療科目に、具体的な対象疾患を記載すると、よりユーザーの検索意図に合致しやすくなります。 -
対象疾患を具体的に記載する:
例えば、「内科」だけでなく、「高血圧」「糖尿病」「風邪」など、具体的な疾患名を記載します。これにより、症状からクリニックを探している患者さんに見つけてもらいやすくなります。 -
予約動線を分かりやすくする:
オンライン予約、電話予約、初診受付など、予約方法を明確に表示します。予約ページへのリンクを目立つ場所に配置し、患者さんがスムーズに予約できるように設計します。
ポイント2:専門性の表現 – 医師紹介・診療実績・疾患ごとのページ構成
クリニックの専門性を効果的に伝えるためには、医師紹介・診療実績・疾患ごとのページ構成が非常に重要です。
患者さんに「このクリニックなら安心できる」と感じてもらえるよう、情報を具体的かつ丁寧に発信しましょう。
-
医師紹介ページを充実させる:
医師の経歴、専門分野、資格、得意な治療法などを詳細に記載します。顔写真やメッセージ動画などを掲載することで、親しみやすさが生まれ、初診のハードルを下げる効果も期待できます。 -
診療実績を具体的に示す:
治療件数や成功事例、患者さんの声などを掲載することで、客観的な信頼性を高められます。特に数字や事例を交えて紹介することで、専門性が伝わりやすくなります。 -
疾患ごとの専門ページを作成する:
各疾患について、原因、症状、診断方法、治療法などを詳しく解説しましょう。専門的な内容を患者さん目線でわかりやすくまとめることで、検索流入の獲得にもつながり、来院動機の明確化にも貢献します。
ポイント3:内部リンクと構造化データ – 症状→診療科→予約の導線設計
クリニックのホームページ内をスムーズに移動できるように、内部リンクを最適化し、構造化データを活用することが重要です。
-
症状から診療科への導線を設計する:
例えば、「咳」という症状で検索した患者さんが、呼吸器内科のページにたどり着けるように、内部リンクを設置します。 -
診療科から予約ページへの導線を設計する:
各診療科のページから、オンライン予約ページや電話予約の案内ページへスムーズに移動できるように、内部リンクを設置します。 -
構造化データを活用する:
構造化データとは、検索エンジンにWebサイトの内容を正しく伝えるための記述形式です。構造化データを適切に設定することで、検索結果にクリニックの情報がより分かりやすく表示され、クリック率の向上につながります。
| 構造化データの種類 | 説明 | 設定する情報 |
|---|---|---|
| LocalBusiness | クリニックの基本的な情報を記述 | クリニック名、住所、電話番号、営業時間、診療科目など |
| MedicalClinic | 医療機関であることを明示 | LocalBusinessに加え、専門分野、提供サービスなど |
| FAQPage | よくある質問とその回答を記述 | 質問と回答のテキスト |
ポイント4:モバイルUXと地域性 – アクセス・Googleマップ・音声検索対応
スマートフォンで閲覧する患者さんが多いことを考慮し、モバイルUXを最適化し、地域性を意識した情報を提供することが重要です。
-
レスポンシブデザインを採用する:
スマートフォン、タブレット、PCなど、様々なデバイスで快適に閲覧できるように、レスポンシブデザインを採用します。 -
アクセス情報を分かりやすく表示する:
最寄りの駅からのアクセス、バス停からのアクセス、駐車場情報などを詳細に記載します。 -
Googleマップを埋め込む:
クリニックの場所をGoogleマップで表示し、患者さんが迷わずに来院できるようにします。 -
音声検索に対応する:
音声検索で「〇〇市 内科」などと検索した患者さんに見つけてもらえるように、地域名と診療科目を組み合わせたキーワードをWebサイトに含めます。
ポイント5:FAQページと症状別コンテンツ – 患者の不安を解消する仕組み作り
患者さんが抱える不安や疑問を解消するために、FAQページや症状別コンテンツを充実させることが重要です。
-
FAQページを作成する:
診療時間、予約方法、料金、保険適用、持ち物など、患者さんからよくある質問とその回答をFAQページにまとめます。 -
症状別のコンテンツを作成する:
例えば、「発熱」「咳」「腹痛」など、症状別に原因、対処法、受診の目安などを解説するコンテンツを作成します。 -
医療広告ガイドラインを遵守する:
FAQや症状別コンテンツを作成する際には、医療広告ガイドラインを遵守し、誇大広告や不適切な表現を避けるように注意が必要です。
これらの設計ポイントを参考に、AIに理解されやすく、患者さんのニーズに応えるクリニックホームページを構築しましょう。
陥りがちなNGパターンと改善策

AI検索に対応したクリニックホームページを作る上で、よく見られるNGパターンがあります。これらのパターンを理解し、改善策を講じることで、AIに正しく情報を伝え、患者さんのニーズに応えるホームページへと進化させることができます。
NG例1:「ごあいさつ」と「診療時間」だけのホームページ
多くのクリニックのホームページでありがちなのが、「院長のごあいさつ」と「診療時間」だけが記載されているパターンです。もちろん、これらの情報は重要ですが、AI検索においては不十分です。
問題点:
- AIがクリニックの専門性や提供できる医療サービスを理解できない。
- 患者さんが抱える症状や悩みに対応する情報がないため、来院につながらない。
- 地域性や強みが伝わらず、近隣の競合クリニックとの差別化ができない。
NG例2:「詳細はこちら」ばかりの内部リンク
ホームページ内に内部リンクを設置することは重要ですが、「詳細はこちら」といった曖昧なアンカーテキストばかりを使用している場合も、SEO効果を十分に発揮できません。
問題点:
- AIがリンク先のページ内容を理解できないため、サイト全体の構造を把握できない。
- ユーザーが求める情報にたどり着きにくく、サイトの回遊率が低下する。
- アンカーテキストにキーワードが含まれていないため、SEO効果が低い。
改善策:構造と意味をAIに“伝える”設計へ
これらのNGパターンを改善するためには、ホームページの構造とコンテンツを、AIが理解しやすいように設計する必要があります。つまり、AIに「このクリニックは〇〇の専門で、〇〇の症状に対応できる」という情報を明確に伝えることが重要です。
具体的な改善策:
- トップページ:診療科目、対象疾患、予約動線を明確に記載する。
- 専門性ページ:医師紹介、診療実績、疾患ごとのページ構成を充実させる。
- 内部リンク:症状→診療科→予約の導線を意識したアンカーテキストを使用する。
- モバイルUX:アクセス、Googleマップ、音声検索に対応させる。
- FAQページ:患者さんの不安を解消する仕組みを作る。
これらの改善策を実行することで、AIはクリニックのホームページを正しく理解し、患者さんの検索意図に合致する情報を提供できるようになります。 結果として、ホームページへのアクセス数が増加し、来院数の増加につながる可能性が高まります。
成功事例に学ぶ:AIO(AI検索最適化)に強いクリニックサイトの特徴

クリニックのホームページをAI検索に対応させることは、集患戦略において非常に重要です。ここでは、実際にAI検索で成果を上げているクリニックの事例を3つご紹介します。これらの事例から、AIに評価されるホームページ設計のヒントを得て、ご自身のクリニックのホームページ改善に役立ててください。
事例1:症状ごとのページ設計でChatGPTに選ばれた内科医院
ある内科医院では、患者さんが検索する可能性のある症状(例:発熱、咳、腹痛など)ごとに詳細なページを作成しました。各ページでは、原因、症状、治療法、予防法などを網羅的に解説。さらに、関連する診療科目や予約ページへのリンクを設置しました。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 症状別ページ | 「発熱」「咳」「腹痛」など、患者が検索する可能性のあるキーワードでページを作成 |
| 詳細な情報提供 | 各症状の原因、症状、治療法、予防法などを網羅的に解説 |
| 内部リンク | 関連する診療科目や予約ページへのスムーズな導線 |
この結果、ChatGPTなどのAI検索エンジンが、患者さんの質問に対して、この内科医院のホームページを推奨するケースが増加。ホームページへのアクセス数と予約数が大幅に増加しました。AIが患者の検索意図を理解し、最適な情報を提供できるホームページとして評価された好例です。
事例2:FAQと予約導線の最適化で検索トラフィックが倍増した耳鼻科
ある耳鼻科では、患者さんからよく寄せられる質問(FAQ)ページを充実させました。「耳鳴りの原因は?」「鼻炎の治療法は?」「子供の滲出性中耳炎について」など、具体的な質問とその回答を丁寧に記載。さらに、各FAQページからオンライン予約ページへの導線を最適化しました。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| FAQの充実 | 患者が抱える疑問を網羅的にFAQ形式で掲載 |
| 具体的な回答 | 専門用語を避け、わかりやすい言葉で丁寧に解説 |
| 予約導線の最適化 | FAQページからオンライン予約ページへのスムーズな導線 |
この結果、検索エンジンからのトラフィックが倍増。FAQページが、患者さんの疑問を解決するコンテンツとして評価され、検索順位が向上したと考えられます。また、予約導線の最適化により、ホームページを訪れた患者さんの予約率も向上しました。
事例3:専門性ページとGoogleビジネス連携で新患数が増えた皮膚科
ある皮膚科では、「ニキビ治療」「アトピー性皮膚炎」「AGA治療」など、専門とする治療分野ごとに詳細なページを作成しました。各ページでは、治療内容、費用、症例写真などを掲載。さらに、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)と連携し、地域キーワードでの検索順位を向上させました。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 専門性ページ | 「ニキビ治療」「アトピー性皮膚炎」「AGA治療」など、専門分野ごとに詳細なページを作成 |
| 詳細な情報 | 治療内容、費用、症例写真などを掲載 |
| Googleビジネス連携 | 地域キーワードでの検索順位を向上 |
この結果、地域住民からの検索流入が増加し、新規患者数が大幅に増加しました。専門性の高い情報を提供することで、患者さんの信頼を獲得し、来院につなげることができました。また、Googleビジネスプロフィールとの連携により、地域での認知度を高め、集患効果を最大化しました。
クリニックのホームページAIO(AI検索最適化)に関するよくある質問
クリニックのホームページをAIO対応にすると、どんなメリットがありますか?
症状ベースの検索やAIによる地域検索に対応できるようになります。これにより、患者さんが自然な言葉で検索した際にクリニック情報がAIに理解されやすくなり、来院につながる可能性が高まります。
従来のSEOとAIOの違いは何ですか?
SEOはキーワードや被リンクを重視しますが、AIOは「文脈」「症状別の情報」「構造化データ」などを重視します。診療科目や対象疾患を明確にすることで、AIが正確に理解できるホームページになります。
医療広告ガイドラインに違反しないための注意点は?
効果を過度に強調した表現や根拠のない記述は避ける必要があります。診療科目・治療法・対応可能な症状など、客観的に確認できる情報を正しく掲載することが大切です。
ポータルサイトに依存しすぎると何が問題ですか?
掲載料や手数料などコストがかさむだけでなく、クリニック独自の強みや専門性を十分に伝えられない点が課題です。自院サイトをAIO対応にすることで、直接の集患力を高められます。
既存のホームページでもAIO対応は可能ですか?
可能です。トップページの診療科目の明確化、FAQや症状別ページの追加、内部リンクや構造化データの導入などを行うことで、段階的にAI対応を進められます。
まとめ:クリニック集客は「AIに伝わる設計」が必須

医療は“信頼”と“文脈”の情報設計が鍵
医療情報を求めるユーザーは、単に症状を知りたいだけでなく、信頼できる情報源と、自身の状況に合った適切な医療機関を探しています。AI検索においては、この“信頼”と“文脈”を考慮した情報設計が不可欠です。クリニックの専門性、医師の経験、提供できる治療法などを、AIが理解しやすい形で構造化し、ユーザーの検索意図に合致する情報を提供することが重要となります。
AIに正しく伝える構造が、地域の患者との接点をつくる
本記事で解説したように、AI検索は症状ベースの質問に対応し、地域性も考慮した結果を表示します。つまり、クリニックのホームページがAIに正しく理解される構造を持っていれば、地域で医療を必要とする患者さんと、最適な接点を持つことができるのです。診療科目、対象疾患、地域情報などを適切に構造化することで、AIはあなたのクリニックを、最適な医療機関として患者さんに紹介してくれるでしょう。
ホームページは“信頼の入口”である
これからのクリニックホームページは、単なる情報発信の場ではなく、“信頼の入口”としての役割を担います。AI検索を通じてホームページに訪れた患者さんは、そこで提供される情報を見て、クリニックの信頼性を判断します。だからこそ、専門性、実績、患者さんの声などを丁寧に伝え、安心して来院してもらえるような設計が求められるのです。
【2025年版】AIO(AI検索最適化)対策に強いホームページ制作の完全ガイド では、AI検索最適化のやり方、業種別の対策や制作ノウハウまで詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
AIO(AI検索最適化)に強いクリニックホームページ設計はAtoZ Designにご相談ください

AtoZ Designでは、医療広告ガイドラインを遵守しながら、AI検索に最適化されたクリニックホームページの設計・リニューアルをサポートしています。
患者さんの検索意図を読み取り、貴院の専門性や強みを正しく伝える情報設計により、AIに評価される構造とコンテンツを構築。
「患者さんに見つけてもらえる」「安心して予約される」サイトづくりで、地域の信頼獲得と集患効果の向上を実現します。
現在お持ちのホームページをAI検索に強い構造へ改修することも可能です。集患に課題を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。